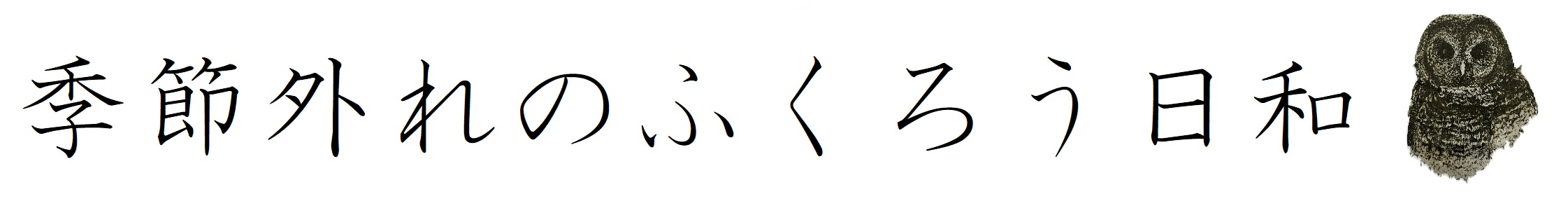作:武田まな
問題の金曜日、里実ワカバは地図と、小説と、スケッチブックを持って図書館に向かった。
図書館に到着すると、いつもの席に彼女はいた。彼女はマッチ売りの少女よろしく切実な表情を浮かべていた。
そんな所在ない姿も今夜で見納めになる。私にはそれを見届ける義務がある、と里実ワカバは心を決めた。
閉館間際、地図と小説を返却すると、里実ワカバはエマ先輩の背中に向かって「さよなら」と言葉を投げた。いや、そう口を動かしただけで言葉は発していない。しかし、呼び止められたかのようにエマ先輩は振り向くのであった。そして、その直後、二人の視線は出会うのであった。静かに、深く、おびえるようにして。
「本当にさよなら」
里実ワカバはそう口だけを動かして締めくくると、その場を後にした。それから、駅に向かって歩きはじめた。その足取りは鉛のように重かった。
もしも、ここで私が走らなければ、彼女は私に追いつくのだろう。そうしたら私は、どうする? この状況を打ち明けるのか? 彼女がシャワーを浴びる前に、私が誰なのか思い出してくれるために。また、『白いモラトリアムサマー』のことを思い出してくれるために。でも、そうしたら彼とあの頃の関係に戻れない。欲望が満たされない。欲望の目的が果たせない。けれども、私を一人にできない、と彼女は言ってくれた(なんでそんなことを言うの、こんな私のために)。ことことに至って彼女なら、この奇妙な出来事を理解してくれるかもしれない。いや、理解してくれるはずだ。そして、力にもなってくれるはずだ。カオルのスケッチブックを持ってきたのは、そのためじゃないのか? だって、私はもうふられているのだし。すでにピリオドを向かえているのだし……。でも、だけど、こんなのって、ああ、どうして私なんだろう? 苦しいよ。
気が付くと里実ワカバは、やりきれない思いから逃げるようにして走っていた。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、と声をあげながら。
暗闇の中で電話が鳴った。
里実ワカバは受話器を手にすると、通話ボタンを押した。
「エミカでしょ?」
「たまげた! てか、どうして私だってわかったの?」エミカは、あけっぴろげに驚いてみせた。それから間もなく、里実ワカバの大人びた声に違和感を覚えたが、夜だし静かに落ち着いた声を発するのも当然かと飲み込んだ。
「たまたまよ」
「たまたまね。あ、そんなことよりワカバ。朗報よ」
「ん?」
「折角の朗報なんだから、もっと食ついてよ」
「そうだった。へへ」と里実ワカバは、ウエットな気配を悟られないよう返事をした。
「その様子だともう知っているわけね。でもって犯人は森野君ね」
里実ワカバは首を左右に振った。違うのよ、エミカ。
「なら話は早いわ。明日、到着する男どもの安着祝いをするわよ」続けてエミカは言った。「学生最後の夏休みなのに、一週間もほったらかしにされたんだから、うんと文句言ってやらないと」
「うん。そうだね。うんと文句言ってやろ」
それから、待ち合わせの時間だの、どこのカフェでお茶をするだの、コーデをダブらないようにするだの、その他もろもろの打ち合わせを済ませてから電話を終えた。
明日、カオルが帰って来る。そのカオル(ミドリ君)が小説の中で言っていた。誰かを好きになるということは、時として誰かを傷つけるのだと。けれど、その事実が存在しなくなれば、あの人の傷は消える。だから、もういいではないか。そりゃ私とて少しは傷ついたものの差し引きゼロだ。いや、プラスだ。私にはカオルがいるもの。めでたし、めでたしじゃないか。
この日以降の小説の内容について、里実ワカバは知らない。晴れて自由の身である。にもかかわらず、その夜は一睡もできなかった。また、明けた朝は、何かから遠ざかってしまったように感じた。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕