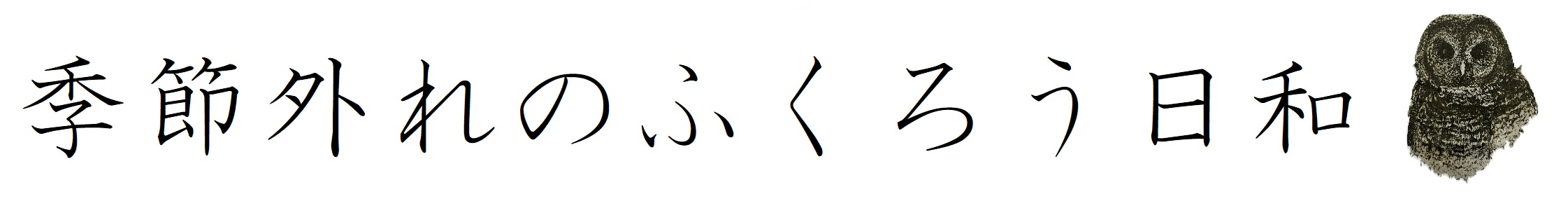作:武田まな
月曜日、エマ先輩は仕事を終えると図書館に向かった。
図書館に到着すると、ひとまず館内を見て回った。それから、カオルのアパートに電話をかけたが、留守だった。そうなれば地図を広げて眺めているほかなかった。まったくもってほろ苦い気分である。
結局、閉館時間までそうしていた。
帰りにスーパーマーケットでレモンを買った。昨夜、冷蔵庫の中のレモンを全て齧り尽くしてしまったのだ。おそらく今夜もそうなること請け合いだ。このペースじゃ幾らレモンがあっても足りやしない。どうしてくれる。
火曜日、昨日と同様、図書館から電話をかけた。
結果は昨日と同じだった。館内の様子も昨日と同じだった。静かだ。一直線に失われているはずの時間が、止まっているかのようだ。そんなのはごめんこうむる。昨日と違う点を探さねば。
思いのほか直ぐに、昨日と違う点を見つけることができた。それというのは、あの場所の地図が貸し出し中になっていることだった(昨日はあった)。まさか、カオル? あり得る。可能性はゼロじゃない。と同時に、カオル以外の誰かが借りていった可能性もゼロじゃない。どっちだろう? と思索にふけていたら雨が降ってきた。これも昨日と違う点だ。昨日と違う点が増えていく。良い兆しなのだろうか?
水曜日、依然地図は貸し出し中のままだった。目下、この事実だけがカオルに繋がる手がかりのように思えた。
ともあれ、いつもの席に腰を落ち着かせると、カオルにまつわる枯れ木も山の賑わい的な仮説をひねり出すことにした。
そうしていると、不意にめまい襲われた。息苦しい。体が重い。けど、倒れてのたうちまわるほどじゃない。大丈夫、すぐ治まるはずだ。昼間の猛暑のせいで疲労が蓄積しただけのこと。いずれにせよ空腹のままは危険だ。血糖値を上げる必要がある。
自動販売機でミルクティーを買うと、ベンチに腰掛けてゆっくりとすすった。甘い液体が干上がった胃に流れていくのが手に取るようにわかった。気分も良くなった。ホッとした。
正直に話そう。いつかこういう日が訪れると、心のどこかで思っていた。どんな物事にも始まりがあり、終わりがあるからだ。そもそもアルファからオメガまでが、一つなのだ。切なくてほろ苦いのは当然なのだ。そんな過去が積み重なるからこそ、人は成長するのだ。背負う過去が少ないガールから、背負う過去が多いウーマンへと。……だからどうした。
エマ先輩は窓ガラスに息を吹きかると、そこに文字を書いた。
一抹の不安に怯えるな。私にはレモンがある。それどころか、まだ過去じゃない。終わっちゃいない。カオル……。
木曜日、私とて耐えられないことだってある。誰でもいいから今の状況を5W1Hにそってわかりやすく丁寧に説明してくれ。いや、カオルの行方だけでもいいから教えてくれ。いや、あの場所が見つかったことだけでも彼に伝えてくれ。
私はとんだ大嘘つきである。行方なんかよりも、あの場所のことなんかよりも、ただただ彼に会いたい……。
照明が消えた舞台の真ん中に一人取り残された気分だ。だからなのかもしれない。鼻歌なんぞ歌ってみようと思い立ったのは。さしずめ曲は『仰げばとうとし』と言ったところか。
鼻唄を歌っていると、カオルと過ごした夏の記憶が胸をかすめていった。記憶は私を癒すものでもあり、私を傷つけるものでもあった。
金曜日、カオルが制作した地形図を眺めていたら、背後から視線を感じた。
振り向くと一人の女の子と目があった。カオルじゃなかった。かといって舌打ちすることかね。
それから、私は指で唇を叩きはじめた。一回、二回、三回、四回。そして、五回目を叩こうとしたときだった。指がぴたりと止まった。今の女の子、日曜日に時間を尋ねてきたワンピの子じゃないか! それに彼女が手にしていたのは、あの地図ではなかったか。そんなことより、カオルの物とおぼしきスケッチブックを抱えていたではないか。彼女、何か知っているかもしれない。間違いない。いや、待て。私の勘違いかもしれない。人は見たいものしを無意識に作り出し見てしまうアレだ。だとしても迷っている場合か!
それから、私は館内を足早に探し回った。が、彼女の姿は見当たらなかった。ということは、外か!
図書館の外に飛び出すと(危うく自動ドアに激突するところだった)ネオンに吸い込まれる寸前のレトロガーリーなシャツワンピースを視界に捉えることができた(よし、全力で追いかけるまでだ)。
スーツにパンプスでは、走るのに困難を極めた。そんなことより、どうして彼女まで走っているんだ? 待って、お願い、私から逃げないで……。
往来の隅にうずくまり足をさすっていた(熊の着ぐるみにぶち当たらなければ……)。そんな私の姿が哀れに見えたのか、男どもをはべらしたOLがふるって声をかけてきた。でもって、耳を塞ぎたくなるような泣かせるお言葉を頂戴する羽目になった(いいからほっといてよ! パイでも投げてやろうか!)。
アパートに帰宅すると、照明も付けずにベッドに倒れ込んだ。もう一歩も動けなかった。地球の中心へ引き寄せられないよう重力にあらがうことしかできなかった。
あの彼女、私のことを知っているとみえる。図書館で目があったとき、身を隠すようにして立ち去ったのが何よりの証拠ではないか。時間を尋ねてきたときだって、たまたま近くに居合わせた人に声をかけた様子じゃなかった。私を追って走ってきた様子だった。つまり私目当てだった。でも、何故……。面と向かって何かを確かめるためだ。その何かとは……。そうか、時間か。まさか二人だけのあの時間? ほーたまげた。そういうことか。フフフフ……。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕