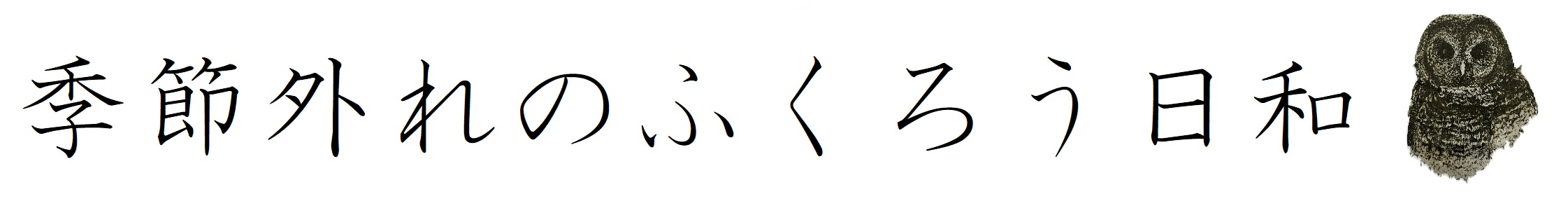作:武田まな
これが今に至るまでの経緯である。何度も思い返してみたが、目新しい何かは発見できなかった。さてと、二度目の電話をかけるとするか。
そしてエマ先輩は、公衆電話にテレフォンカードを差し込むと、プッシュボタンを押した。はやくカオルの声が聞きたい。でもって、うっかり寝過ごしました、とかうんぬん私に告げてくれ。
……
エマ先輩は受話器をやおら下した。なしのつぶてである。
私はカオルのアパートの電話番号しか知らない。彼のアパートがどこにあるのか知らない。最寄りの駅すら知らない。わざわざ訊かなくても、確かめなくても、二人にはあの時間、つまり二人だけのあの時間があるから、そんなの知らなくても大丈夫だと高を括っていた。また、甘えてもいた。二人だけの時間に? 彼に? シチュエーションに? 全てか。さぞかしまぬけである。ともかく、なんともいえない気持ちのまま、ここで彼が来るのを待つしかないようだ。ことここに至って、今は……。
結局、夕方になってもカオルは現れなかった。切実。どうして昨日、あの場所を見つけたと直ぐに言わなかったのだろう? もし言っていれば、こんな風にならなかったのかもしれない。そう思うと自分に腹が立ってきた。このアホンダラ。
「あ、あの」
駅に向かって歩いていると、レトロガーリーなシャツワンピに髪をボヘミアン風のツインの三つ編みに結った女の子が声をかけてきた。彼女は息を切らしていた。その格好でこの暑い中ジョギング? そんなわけないか、とエマ先輩は考えながら返事をした。「どうかされました?」
「えっと、すみません」里実ワカバは息を整えながら、手にしていた本をギュッと握り締めた。「今……何時ですか?」
「今って 今?」
「はい、今です」
腕時計の時間を確かめると、エマ先輩はにべもなく告げた。
「午後四時五十五分ですよ」
それは世の中の並列化された時間ではなく、二人だけのあの時間だった。したがって、エマ先輩はゴメンね、という意味も込めて軽く首をすくめてみせた。
「あ、ありがとうございます」と里実ワカバは、どぎまぎしながら礼を言った。それから、お辞儀をして足早に立ち去った。これで確かめられた。間違いない。この状況『白いモラトリアムサマー』に書かれている内容と同じだ。でも、まさかこんなことって信じられない……。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕