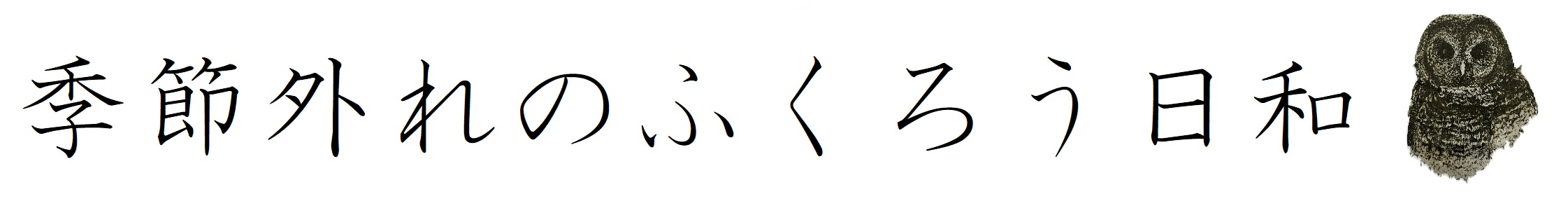作:武田まな
雨が上がりの晴れ間が覗きはじめている空の下、エマ先輩は大学の屋上にいた。そして、クロワッサンで口の中を一杯にして一篇の詩を思い出していた。
そんな時だった。眼下に広がる景色の中から、スケッチブックを抱えて歩く『仰げば尊しの彼』を見つけたのは。
彼は図書室に向かっているようだった。そして、小さな光の粒と化した雫が付着した芝生の上を歩いているのだが、彼の歩いた箇所だけ雫が落ちて芝生が青く見えた。絵に描いた様なシチュエーションだな、とエマ先輩は思った。と同時に、あることを思いついた。
紙飛行機を飛ばして彼のところに届いたら声をかけよう、うむ。
それから、エマ先輩はバッグからレポート用紙を取り出すと、紙飛行機をこさえた。そして、翼の角度を調整すると、目を閉じて一周回わりテイク、オフ。
紙飛行機は弧を描きながら高度を下げていった。そして、彼の足元に着地した。
エマ先輩は口をあんぐり開けていた。どうしてくれる。ともあれ、迷うなんてらしくもない。腹を決めろ。
「ねえ、そこの人」
しかし、彼は全く気付いていない模様。続けてエマ先輩は声をあげた。
「ねえ、そこのメガネの人」
……
彼は足元に目を落としたまま小首をかしげていた。だからエマ先輩はこう言った。
「そこの仰げば尊しの人」重ねて「季節外れの仰げば尊しの人」
そう声をかけられて、彼は一篇の詩を思い出した時のような顔した。そして、屋上にいるエマ先輩に気が付いた。
「それって、僕のことですか?」
「オフ、コース」とエマ先輩は答えた。「ねえ、その紙飛行機ひろってくれない?」
彼は紙飛行機をひろうと、エマ先輩を見上げた。
続けてエマ先輩は言った。
「あのさ、お願いがあるんだけど」
「もしかしてそのお願いって、この紙飛行機を屋上に届けるとかですか?」と彼は、先取りして言った。
「yes」とエマ先輩は言い、大げさに首をすくめてみせた。
彼は紙飛行機を手に屋上に向かった。そして、階段を上り終えると、屋上に通じるカフェオレ色の扉を開けた。すると柵にもたれた女性の姿が目に留まった。長く艶やかな髪と、手首に巻かれたオリーブ色のリボンが、彼の目に印象的に映った。
「あ、きたきた。サンキュー」とエマ先輩は言い、右手を差し出した。
「はあ」とだけ彼は言い、エマ先輩の手のひらに紙飛行機を乗せた。そして、会話の接ぎ穂を探すことにした。が、そう易々見つかるものではないと相場は決まっている。
「どうしたの?」
「ここ良い場所ですね。静かだし、風が気持ちいいし、空が近いし」案外、直ぐに接ぎ穂は見つかった。というよりも、彼女からそう言うように促された気がした。
「でしょ」
そう答えたエマ先輩の足元には、バッグがあり、缶コーヒーがあり、食べかけのクロワッサンがあり、読みかけのペーパーブックがあった。人間味にあふれた人だな、と彼は思った。「それじゃあ、これで」と彼は言い、スケッチブックを抱え直すと、カフェオレ色の扉に向って歩きはじめた。そう言えば、どうして『仰げば尊し』のことを知っているのだろう? でも、もう遅いか、と思った瞬間、背後から声がした。
「ねえ、空が近くて何を感じた?」
彼は振り向くと、おうむ返しした。「空が近くて何を感じた?」
「そうよ」
少しばかり記憶を巻き戻して答えた。「焼きたてのクロワッサンが無性に食べたくなる、とかですかね」
その答えを受けてエマ先輩は笑った。言ってくれるじゃないか。「私、四年の杜葉エマっていうの。よろしくね」次はあなたの番だと目顔で促した。
「僕は三年の森野カオルです」
「へえ、森野カオルって言うんだ。おまけに年下か」
「どうやらそのようで」
「でも納得」
「どうしてですか?」
「さあ、どうしてかな?」エマ先輩は質問をはぐらかすと、指で唇を叩きはじめた。そうやって森野カオルの反応をあれこれ楽しむことにしたのだ。
「あの、杜葉さん」
「なに?」
「一つ尋ねてもいいですか?」
「もちろん。お好きに、なんなりと」
「じゃあ、遠慮なく」一呼吸置くと、森野カオルは言った。「どうして『仰げば尊し』のこと知っているんですか?」
「どうしてって? 森野君。その曲、よく鼻歌で歌っているじゃない。図書室だとか、講義中だとか。きっと、もっと色々な場所でそうしているんでしょ?」とエマ先輩は、こともなげに答えた。
次の瞬間、森野カオルの手からスケッチブックがずり落ちた。
「あの……鼻歌って聴こえるんですか?」
「えっと、森野君?」質問の意味を理解するに、少し時間を要した。「もしかしてだけど、君は鼻歌が周囲に聴こえていないと思っていたわけ?」
「ええ、自分にしか聴こえていないと思っていました」
「今の、今まで?」
「YES」
用心深くデリケートな返事だった。
それを耳にしたエマ先輩は 大胆に笑うしかなかった。謎が解けてその解け方も悪かない、というわけだ。なんだかレモンに齧りつきたい気分だった。
「森野君、あなたってスリリングだわ。想像していた以上、なかなか新鮮」
「嗚呼、どうして今まで誰も教えてくれなかったんだろう?」舌を噛んで死にたい。
「そう落ち込まない」
「けど……」
「ほら、ここは屋上よ。辺りの景色をよく見る」とエマ先輩は言い、両手を真横に大きく広げた。
森野カオルは屋上から見渡せる景色に目をやった。一人の人間が高い場所に立っても、見渡せる景色は限られていた。世界のほとんどは不可視なのだ。それだけ広大なのだ。
彼が景色を見ている間、エマ先輩は『仰げば尊し』を歌いながら、紙飛行機の翼を調整していた。その時、はじめて気が付いたことがあった。というのも、『仰げば尊し』はワルツだったのだ。どうして今まで気付かなかったのだろう? それに、琴線に触れる良いメロディーではないか。思春期に想いをはせたくなるではないか。とくれば、ついこんなことを言ってのけてしまう。
「ねえ、私のことエマでいいわよ。見かけたらいつでも声かけて」
「わかりました。えっと、エマ先輩」
「ま、それでもいいわ。森野」
そしてエマ先輩は、紙飛行機を空に送り届けた。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートと情報を綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕