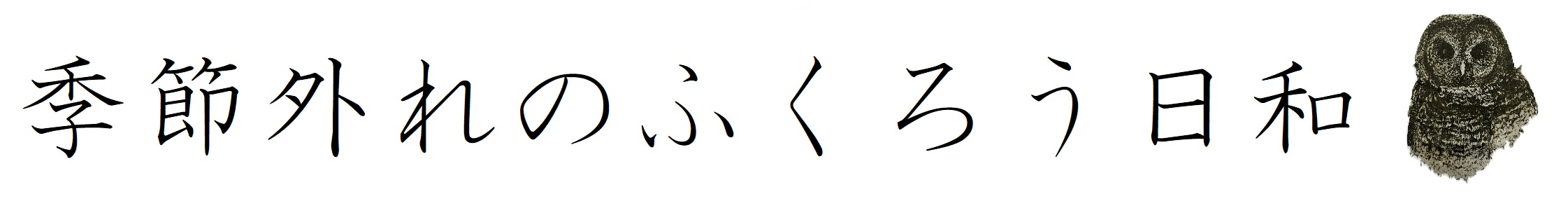作:武田まな
程なくして、あふれんばかりのビールを湛えたジョッキが四つ、テーブルに並んだ。銘々、ジョッキを手にすると、ロマンチックな夜に乾杯してから口に運んだ。火照った唇に冷たいジョッキが触れる。金色の液体が移動しはじめる。脳が快感を受け入れる準備をする。そして、里実ワカバの声にならない声が漏れる。
その声が届いたのか、森野カオルはビールを口にすることなく言った。
「里実、大丈夫か?」
「えっ」
そう声をかけられて、里実ワカバはテーブルの上の白いドット模様に気が付いた(鼻血まで白いというのか)。
森野カオルはポケットをまさぐった。しかし、小銭と毛玉が指先に触れるだけだった。「桃井、ティッシュあるか?」
「ぷはー」エミカは上唇に付着した泡を拭うと答えた。「ん、あるけど何で?」
「ほら、里実が」
「ワカバがどうしたの?」里実ワカバの様子を見て「なんともないじゃない」
「森野、まずはビールだ。美味いぞ」高橋は鼻の下に泡を付着させたままそう言った。
「ビールより、里実の鼻血が先だろ」と森野カオルは、口をついた。
「はあ、鼻血? なに言ってんだ」
「森野君。ワカバ鼻血なんか出してないわよ」
「そんなわけないだろ」
森野カオルは紙ナプキンを里実ワカバに手渡した。
「ワカバからも何か言ってよ」とエミカは言い、首をすくめた。
「それが一番だな」けろりと高橋。「やれやれ」
どうかしている、と森野カオルは思い、今の状況をわからせるため声をあげることにした。しかし、それよりも先に、里実ワカバは小さな声で言った。
「もういいの。カオル」紙ナプキンをおずおずと握りしめて「いいの。私のことは、大丈夫だから」
「大丈夫なわけないだろ」
「もういいの」
「何だよそれ」
「もういいのよ。大丈夫だから」ドット模様が鼻血なのか、涙なのか、わからないや。その区別すらできないや。
「里実……」
「ごめんね」そう喉から言葉を押し出した。それから、もう一度。「ごめんね。カオル」
「なんで謝るんだよ」
「……」
里実ワカバは立ち上がってテーブルを離れた。それから、店を後にするとあてもなく走り出した。いや、逃げたのだ。だって、私には最後までやり遂げられないと知ってしまったからだ。湿っぽい覚悟でことことに至ってしまったと知ってしまったからだ。とことん自分が嫌になる。ただただ、イカれていやがる。どうかしている。もう限界だ。そう、もう限界。足が重い。走れない。歩けない。立っていられない。倒れそうだ。呼吸すら危うい。全身が痛い。心も痛い。痛いのはもう御免だ。誰か、助けて!
その時だった。後ろから手を掴まれたのは。
私は私の手を掴んだ誰かが誰なのかを確かめず、その人の胸を叩いて罵りはじめた。
その人は何も言わず私の言葉を受け止めていた。それが辛かった。だから、更に激しくその人を罵っていると、あやうく気を失いかけた。私はその人の支えがなければ、立っていることさえままならなくなった。そんな状況にも関わらず、私はわめき続けた。世界一面倒な女である。ここにそう断言させてもらう。
どのくらいの時間、そうしていたのだろう。その人は大人しくなった私を背負うと、大通りに出てタクシーをひろってくれた。
タクシーでの移動中、私は震えながら泣いていた。そんな私を、その人は抱きしめていた。
いつしか心が温かくなった。震えが止まった。涙も止まった。いや、涙については枯れたのか。
やがて、タクシーは見覚えのあるアパートの前で停車した。私たちはタクシーを降りた。
そして私は、あの人に鍵を返した。その鍵でドアが開いた。すると部屋の中は真っ暗だった。色彩は夜の闇に包まれていた。ホッとした。
それから、私は受け入れるだけだった。そして、それは私が望んだことでもあった。そう、私の欲望が満たされたのだ。欲望の目的が果たせたのだ。それなのに、そのはずなのに……。
「カオル、まだ起きている?」
「うん、起きているよ」
「あのね」と里実ワカバ。そして、森野カオルの手に、手を重ねた。「欲望の目的ってね。満たすことじゃなかったのよ」
里実ワカバの体温を感じながら、森野カオルは繰り返した。
「満たすことじゃなかった?」
「そうよ。欲望の目的はね。欠けることだったのよ」
「どうして?」
「全ての欲望が満たされてしまったら、欲望のアイデンティティーが失われてしまうからよ。だって、もう何かを満たすことが叶わないんだもの。もう満たすものが存在しないんだもの。そうならないために、つまり欲望が欲望であり続けるために、欲望は何よりも欠けることを求めていたのよ。ようやく、それに気付くことができたの、私」
続けて里実ワカバは言った。
「カオル。聞いてほしい話があるの」
森野カオルはそっと頷いた。
それから、里実ワカバは『白いモラトリアムサマー』と、この夏の出来事を話しはじめた。
過ぎ去ったこの夏の出来事(記憶)は、どれもこれもこの私が存在した証だった。また、過ぎ去ったこの夏の出来事(記憶)は、この私を傷つけるものでもあり、この私を癒すものでもあった。そんな記憶の果てに、今私はここにいるのだと強く実感することができた。
全て話し終えた里実ワカバは、付け足すように言った。
「この話を信じるとか、信じないとか、そんなのはどうでもいいの」
「重心はそこに無いんだね」
「うん」
「そっか」と森野カオルは言い、暗闇の先にある腕時計を見つめた。「ねえ、ワカバ。今からその湖に行ってみようよ。そこに行けば何かわかるかもしれないし、何か見つかるかもしれない。根拠は無いけどそんな気がするんだ」
「今って、今から?」
「そう、今から。色彩が夜の闇に包まれている今の内に」
「わかったわ。行きましょう。木崎湖へ」
そして二人は、ベッドから起き上がると身支度を整えた。それから、チープな軽自動車に乗り込んで長野県へと向かった。
長野県までの道すがら、二人はお腹が減るとビスケットを齧り、インスタントコーヒーでのどを潤した。また、眠くなると駐車場で仮眠をとった。ビスケットやらコッヘルやらブランケットの類は、森野カオルのザックの中から出てきた。また、例のプレゼントもザックの中から出てきた。
「遅くなったけど、はい」と森野カオルは、心がある声で言った。
「ありがとう。嬉しい」包みを解いて「これアンクレット?」
「そうだよ」
「そっか」と里実ワカバは言い、アンクレットを身に着けると片足を上げてみせた。「どう、似合う?」
「うん。似合っている。のぼせるくらい魅力的だよ」
里実ワカバははにかんで言った。
「バカ」
東の空に明けの明星が瞬きはじめた頃、二人が乗る軽自動車は長野県に到着した。しかし、目的地でもある木崎湖はまだ先である。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕