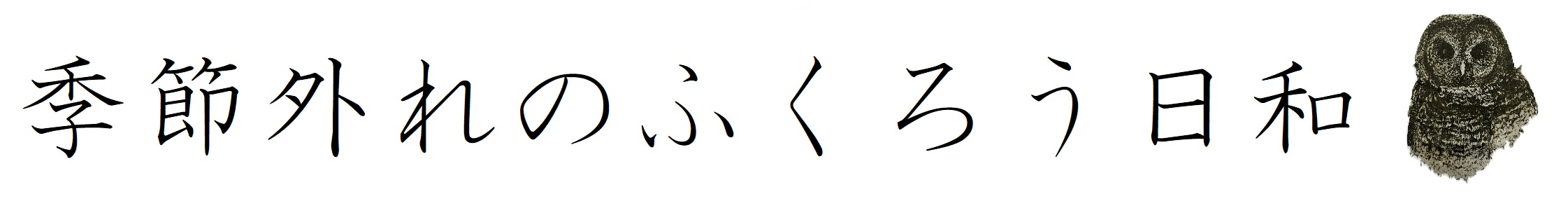作:武田まな
「ワカバ、ワカバ、ねえ、待ってよ」そう呼び止めたエミカの声は、打って変わってはずんでいた。それから、指を差して「ほらほら、あそこ!」
そして里実ワカバは、エミカが指差す方角にやおら視線を移した。すると日焼けした男どもが、こっちに向かって歩いて来る姿が目に入った。と同時に、里実ワカバはハッとした。というのも、森野カオルの背後には、夕焼けの写真が使われた大きな看板があったからだ。
ねえ、なんでよ。どうしてよ。夕焼けは嫌いだって言ったじゃない。はやく忘れさせてよ。楽にさせてよ。いい加減にしてよ。いったいどこの誰に向かって嘆いているんだか、私……。ハハン、今この瞬間『白いモラトリアムサマー』を読んでいる人に向かって嘆いているのか。だからって、それを知ったからって、なんなのさ!
そう言葉を投げ捨てたときだった。里実ワカバの目に映る景色から、色彩がゆっくりと消えていった。そして、モノクロームのスケッチのように白と黒になった。驚きのあまり、彼女の思考は停止した。
……
そうとは知らず、森野カオルは言った。「ん? レモンの香りがする」
「森野君、開口一番おかしなこと言うのね。てことは、相変わらずってことね」とエミカは言った。それから、フィールドワークの末、野生化しつつあるオスどもに向けて「おかえりなさい。おバカさんたち」
「おう、ただいま」と高橋は言い、二人の女子に向かってガムをパチンといわせた。
「うん、ただいま」と森野カオルも言い、二人の女子に向かって軽く微笑んだ。
「……おかえり」と里実ワカバは、声を絞り出した。
「里実。どうした? 何かあったか?」
「ううん、何でもないよ」かえってモノクロームの方が、夕焼けの赤が分からないだけましじゃない。そんなことより、私はこのモノクロームで描かれた絵のタッチを知っている。そう彼の絵のタッチそのものではないか。だから何てことはない。「いや、撤回。何でもあるよ。一週間もほったらかしにされたっていう何でもが。ちゃんとその穴埋めをしてよね、カオル」
エミカは何度も深く頷くと言った。
「ワカバの言う通りよ。学生最後の夏休みなんだから、最後の最後までダンピングするつもりなんてこれっぽっちもないわよ」
「あ、そうだエミカ」と高橋は言い、ポケットから包み紙を取り出した。「僕だってダンピングするつもりなんかないよ。ほれ」
「あ、ありがとう」小さな包み紙を受け取ると、エミカの頬が緩んだ。「物につられた安い女に見られるじゃない」
「誰もそんな風に思わないよ」
「もうバカ」
「里実」と森野カオル。
「ん?」
「プレゼント、うっかりザックの中に忘れてきちゃって。だから後で」
「あり……がと」プレゼント? お土産じゃなくて? 嬉しい。「ねえ、スニーカーの紐、解けているよ。カオル」
「あっ」
「へへ、相変わらずだ」
「そうそう、さっき森野君が言ったレモンの香りで思い出したんだけどさ。合流する前、わけあって綺麗な女の人に話しかけられたのよ。ドキッとするくらいオシャレで、シュッとしていて、レモンみたいに良い匂いがして……」とエミカの声が小さくなる。それから、小首を傾げて「そういえばあの人、どこかで見たことがあるような、ないような。ねえ、ワカバ知っている?」
里実ワカバはこともなげに答えた(ごめんね、エミカ)。
「もしかして有名人だったりして。だから、どこかで見たことあるとか思ったんじゃない?」
「へえ、有名人か」と高橋は言い、ガムをパチンと鳴らした。「その有名人とやらを見に行こうか、森野」
「見てどうするんだよ」
「そうさな、握手してレモンの匂いがするか確かめてみようかな。クンクン」
しまった。あらぬ方向へ野性化していやがる、とエミカは悟った。したがって即効性のある更生プログラムを施行させるため、彼女の中の最高裁判である判決がくだされた。
エミカの判決がくだされるよりも先に、森野カオルと里実ワカバは他人のふりを試みたが、間に合わなかった。したがって、いらぬ注目を浴びることになった。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕