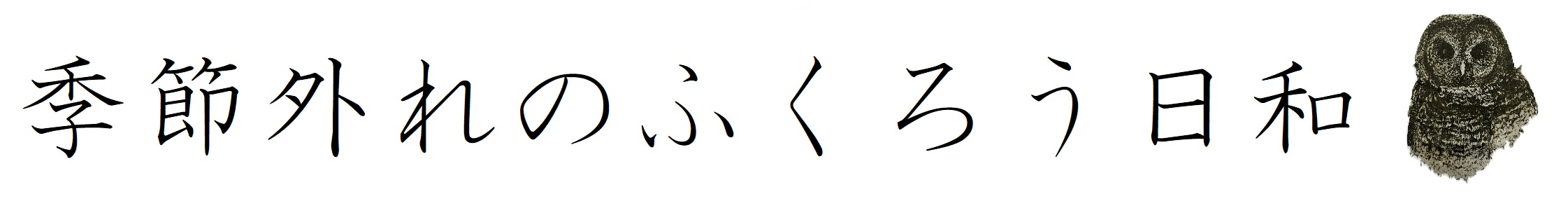作:武田まな
怪しげな物音で目が覚めた。
怪しげな物音は、ドアの方からした。それはノックの音に似ていた。カオルなの? いや、今度こそ人は、聞きたい音を無意識に聞いてしまうとかいうアレだ。にしても、いけすかない音と声だ。その上、近所迷惑だ。やれやれ。
「今、開けるから静かにして」とエマ先輩は、投げつけるように言った。そして、ベッドから体を引きはがした。
「もう、おねーちゃんてば返事が遅い」とマミは、ムッと言葉を返した。
それに対する返事を省略して、エマ先輩はドアを開けた。
「てっきりいないのかと思ったよ」マミは部屋の中にずかずかと入ってくると、ザックとレジ袋を床に置いた。それから、照明を点けて「でも、居るってわかっていたからノックし続けたんだけどね。てか、なにこの部屋の荒れ模様」
部屋の中にはレモンの皮だの、紙飛行機だの、洗濯物だの、ペーパーブックやムックだのが散らかっているわけじゃなかった。全て綺麗に整頓されているにもかかわらず、マミはそう言ったのだ。気配を感じ取って。
またしてもエマ先輩は、それに対する返事を省略した。
「ど、どうしたの? おねーちゃん。何かあったの? チャーミングな妹に話してみ?」
「ねえ、今日は金曜日よ。明日来るんじゃなかったの?」とエマ先輩は、くぐもった声で尋ねた。
「ワンピじゃなくて、おねーちゃんに会えると思ったら待ちきれなくてさ。最終電車に飛び乗って来ちゃったわけ」あわよくば、金曜の夜だし彼氏の顔も拝めるかもしれない、と言う魂胆もあったのだが、あ、そう言うことか。今まさにエマージェンシーってことか。たいそう折の悪い日に来てしまったもんだ。「そうだ。あたし晩御飯まだなんだ。突然、押しかけておいて能天気にお相伴にあずかるわけにもいかないじゃない? だから、スーパーで食材買って来たの。気が利くでしょ? それじゃあキッチン借りるね。もちろん、おねーちゃんの分も作るからさ。その様子だと晩御飯まだなんでしょ?」
「私の分はいらないわよ」
「食欲ないの?」眉をひそめて「無理してでも、何か食べたほうがいいよ。元気出ないし、体に悪いし、夏風邪ひくよ」
「……」
やれやれ。マミは口調を変えて言った。
「ねえ、スーツがシワだらけ。髪もぐしゃぐしゃ。マスカラが落ちてパンダ目になっている。おまけに目も真っ赤。せっかくの美人が台無し。何があったか知らないけど、シャワーを浴びることくらいできるでしょ?」
エマ先輩は叱られた子供よろしく小さく頷いた。それから、大人しくバスルームに向かった。
こりゃ重症だな。心の痛手を癒すのにも骨が折れそうだ。もとかく、ナポリタンでもこさえるとするか。
そしてマミは、服を脱がすみたいに玉ねぎの皮を剥きはじめた。一枚、二枚、三枚……。
裸になったエマ先輩は、体がふやけるまで熱いシャワーを浴びた。それから、冷たいシャワーを浴びてふやけた体を引き締めた。体がジーンとした。と同時に、人心地がつき食欲もわいてきた(かたじけない、マミ)。
正面に目を向けると、鏡の中に濡れた私がいた。この私とやらが鏡に映った実存を眺めているだけのこと。この私とは、私であるといったトートロジー。そう言えば、この私という自我は過去という記憶がつくりだした虚構であるうんぬん何かで読んだことがあったな。いったい記憶とはどんな代物なのか知りたいものだ(白くて丸い小さな物質が脳内にあったりして? たいそう月並みな想像力である)。
エマ先輩はバスルームから手を伸ばすと、タオルをたぐり寄せた。それから、体を拭いていると、白くて丸い物質から糸口を見つけた。
そうだ! あのワンピの彼女、学生時代に何度か見かけたことがあったじゃないか。私だって彼女のことを知っていたじゃないか。よし、もう一度整理しよう。過去(記憶)をブレンドして。
エマ先輩は指で唇を叩きはじめた。
彼女は私に時間を尋ねてきた? じかん、ジカン、と言えば学生時代、時間にまつわる小説を読んだことがあった。確かタイトルは『白いモラトリアムサマー』だったな。でもって、偶然再会した男女が二人だけの時間を作る話だった。この夏、私とカオルがしたように。あっ……。
エマ先輩の呼吸が止まった。思い出したかのように呼吸が再開すると、騒ぎ立つ胸を抑えて思考を前に進めた。
二人だけの時間を纏った彼(ミドリ君)と彼女(レモンさん)は、とある場所を探すことになったのだ。その過程で不幸なピタゴラス装置が働き、二人の時間もとい夏の思い出が失われてしまうのだった。いや、少し違う。思い出が失われるのではなく、事実が消えるのだ。そもそも存在しなくなるのだ。したがって、二人は再会する前の自分(この私)とやらになってしまう。だから、心に痛手すら残らない。カタルシスもへったくれもありはしない。救いようがない。いや、その必要すら無い、と言うべきか。
次の瞬間、指で唇を叩く仕草が止まった。
いや、救いがあった! そうあったではないか。はじめに小説と現実が重なっていると気付いた登場人物(ミントさん)がいたではないか。つまり、彼女がミントさん……。
ともかく、一刻も早くあのワンピの彼女(ミントさん)を探し出さなくては。待って、落ち着け。彼女も小説の中で言っていたではないか。こういう時は急がば回れと相場は決まっている。まずは今の状況を整理するのが先だ。
小説と現実が重なったのならば、既にカオル(ミドリ君)からは事実が失われている。しかし、私(レモンさん)からは事実が失われていない。そこがポイントになるはずだ。だとしたら、彼女(ミントさん)を見つけ出すよりも先に、私(レモンさん)の腕時計の時間が元に戻らないようにすることが先決だ。したがって、小説の中からそのシーンを思い出す必要がある。私とて事実が失われてしまえば、お手上げだ。そもそも、そんなのまっぴら御免だ。それに、彼女を一人にできない。だって、あんな結末だなんて……。さっするところ今が胸突き八丁ってわけか。よし、やってやれ杜葉エマ! 過去という記憶の迷路を駆けずり回れ。思い出していることを忘れるくらい思い出してみろ。今、この私のアイデンティティーはその一点に尽きる。可能性を手放すものか。無かったことにさせるか。カオル! ワカバ! ん、ワカバ? あの彼女の名前だ。里実ワカバ(何故、その名前を知っている、私?)。それに思い出した。屋上でカオルと初めて話したとき、その前にレモンさんの事実が消えるシーンを読んでいた。
次の瞬間、エマ先輩は叫んだ。
「マミ! 待って、触らないで!」
マミはパスタを茹でるに当たりキッチンタイマーを探していた。しかし、キッチンタイマーは見当たらなかった。代わりにナイトテーブルの上にある腕時計と目覚まし時計を見つけた。それぞれ二つの時計は異なる時間を指していた。どっちが正しいのだろう? とマミは疑問に思った。また、社会人のくせに人間味にあふれた奴め、とも思った。ともかく、コードレスの受話器を手に持ち117とプッシュボタンを押した。正確な時間を確かめる必要がある。パスタを茹でるのはそれからだ。
「ピッ、ピッ、ピッ、ポーン、午後九時十二分十五秒をお知らせします」
そしてマミは、腕時計の時間を九時十二分十五秒にセットした。すると、バスルームから大きな音がした。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕