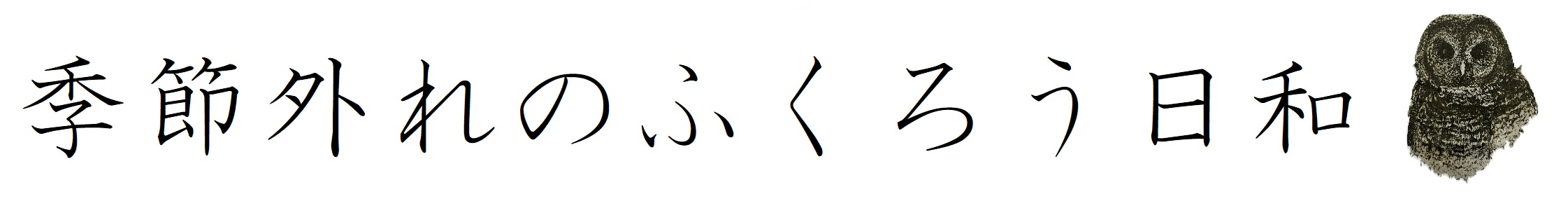作:武田まな
二人は森野カオルのアパートメントに到着した。するとアパートメントの前に無骨なジムニーが路駐してあった。しかし、持ち主の姿が見当たらない模様。つまり、そういうことか、と森野カオルは合点した。
森野カオルがドアノブを回すと(やっぱり、鍵が開いていやがる)案の定、部屋の中には不届き者がいた。
不届き者は横になって車のキーと、アパートメントのキーをもてあそびながらラジオを聴いていた。ラジオからは荒井由実の曲が流れていた。
「ハハン。仲良く朝帰りというわけか」と高橋は思わせぶりに言い、ガムをパチンといわした。「それとも、朝の散歩がてら仲良く買物といったところか」
「は? 何言っているんだ。里実とは今ばったり会ったんだよ。というよりか」
森野カオルの話を遮るように高橋が言った。
「鍵を隠す場所が単純すぎるんだよ。森野」
「もしかして玄関マットの下とか?」と里実ワカバは、早押しクイズよろしく答えた。
「うげ、どうして里実までわかるんだよ」
「さしずめカオルのことだから、灯台下暗しとかうんぬんでしょ?」
続けて里実ワカバは言った。
「そんなことより高橋君。カオルの言った通りなんだからね。本当に今ばったり会ったんだからね」念のためもう一度「それ、本当だからね」
「ふーん」と相槌を打って起き上がり「ま、そう言うことにしておくか」
あろうことか不届き者にイニシアティブを取られてしまった、と里実ワカバは思った(おいそれと、そうはさせるか)。
「変な風に誤解しないでね。タカハシ君」と里実ワカバは、歯ぎしりしながら言った。
それを要約すると、このことを吹聴して回ったのならあなたの身の安全は保障されない、とでもいったところか。高橋は鼻で笑うとガムを膨らませた。次の瞬間、意に反してガムが破裂した。たまげた、里実ワカバの鋭利な視線を浴びてガムが破裂したとでもいうのか。とんだ能力をお持ちとみえる。こういうときは陽気に笑うに限る。笑う門には、という例のあれだ。そして高橋は、笑いはじめた。
「アハハハ」
「ウフフフ」と里実ワカバ。
「二人とも急に笑い出して、どうしたんだよ」
「どうもしないわよ。ねえ、高橋君」
「どうもしないさ。なあ、里実くん」
「ワッハッハッハッ」
森野カオルは笑い合う二人を尻目に食材を冷蔵庫の中にしまった。
「んで、高橋。何の用だ?」
「はあ、何言っているんだよ。昨日、電話で最終確認したじゃないか」
「あ、そうか。もうそんな時間か。というよりか、今日だって忘れていた」
「おいおい、冗談だろ」
「直ぐに準備するから、これでも食って待っていてくれ。ほれ」
高橋はバナナをキャッチした。
「冗談じゃないのかよ。ほら」
森野カオルはアパートの鍵をキャッチした。
「ねえ、これからどこかに行くの?」と里実ワカバは尋ねた。
「エデンの東までフィールドワークしに行くんだよ」と高橋は答えた。
「東じゃないだろ。北だろ」
パッキングしながら森野カオルは、そう口を挟んだ。
「向かう方角は北だけど、気持ちは東だ。待ってろ、東にある北の大地! ん? 北にある東の大地か」
「まさか北海道! こ、これから?」思うにこの二人は、東京から北海道までの距離をわかってらっしゃるのだろうか?
「もちろんだとも。これからイカしたジムニーで北海道とやらに向かうのさ。だけど出発できずにご覧の有様ってわけさ」
「悪かったな」
そっか、世界地図の大きさで東京から北海道までの距離を把握していやがるのか、と里実ワカバは合点した(目と鼻の先だと思っていやがる。これだから男というやつは……)。
「で、いつ帰って来るの?」
「そうさな……早くても一週間後ってところかな」バナナを頬張って「ともかく、その間、森野を借りるよ。里実くん」
「いいけど……」いいけどって、私。でも、ことことに至ってカオルの身になにが起きたのか考えられる。それに『白いモラトリアムサマー』の続きが読める。また、あの人と物理的な距離が生じることは、色々と都合がいいのかもしれない。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕