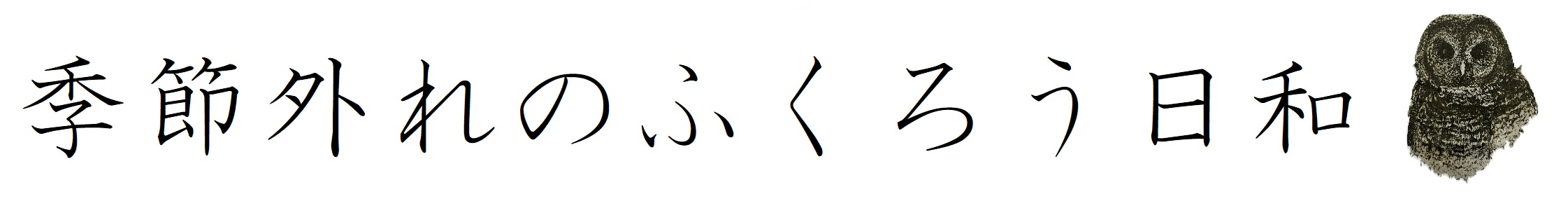作:武田まな
里実ワカバはポージングを続けながら思った。
今までの私は、大胆になるきっかけを外部からの偶発的な要因に求めていた。今夜のように自らの手でその要因なるものを作ろうとはしなかった。ただただ予見可能な未来が訪れる小さな日常の中に身を置いていた。それは、予見不可能な日常が怖いからだ。それに、自分以外の誰かを信じることも怖いからだ。その中にうっかり好きな人も含めてしまうなんて、私はバカか……。
そういえば、カオルのあくび、もう何回目だろう? きっと無意識でしているのだろう。そんなことより私は、あくびを糸口に疑問を解決してまった。というのも、昨日、電話がつながらなかった理由。不在だった理由。そして、電話の後に何があったのか。当たってしまう女の感たるや、厄介。
里実ワカバは眉間にシワを深く刻んだ。ささやかではあったが、不満を意思表示したのだ。
彼女の意思表示が届いたのか、森野カオルの手の動きが鈍くなった。その折を見逃さず里
実ワカバは言った。
「あのさ、カオル」理由はどうあれ、今、私だけを見ている。それは私のたっての願いでもある。ともかく、信じてみなくては。「最近、紙飛行機の先輩と会ったの? えっと……」躊躇していたら、森野カオルが先取りして言った。
「エマ先輩のこと?」
「そう、杜葉先輩」
「うん」と答えて「二か月くらい前に、偶然、再会したんだ」
「偶然なんだ」
続けて里実ワカバは、ためらいがちに言った。手のひらにグロテスクな湿り気を感じながら。
「あのね。実は今日のランチタイム、カオルが席を外した折、勝手にスケッチブックを見ちゃったの、私。ごめんね」
「……そっか」
「一緒にロケハン行っているんだ、先輩と」
「うん」
「まるで彼女みたい」と里実ワカバは、ポツリと言った。
「そんなんじゃないよ。そんなんじゃ……」と声が小さくなる。それから、テーブルの上の腕時計に目をやった。
「じゃあ、二人の関係って何?」
「それは……」
「じゃあ、カオルは杜葉先輩のことどう思っているの?」ものすごく嫌な女である。そんなことより、はっきりさせて大丈夫なのか、私。
森野カオルは一呼吸置くと静かに言った。先輩のことを意識していると。先輩に惹かれていると。そして、先輩とは終わらない関係でいたいと。
そう告げられて、里実ワカバはワンピースの裾を強く握りしめ言葉を投げつけた。
「それってアガペー? 見返りを求めない愛とかなの? ロマンチックラブとか、モダンラブの類ってわけ?」頭がくらくらする。ああ、私は選ばれなかったのか。
続けて里実ワカバは言った。
「ねえ、カオル。恋愛って人を選別することなのよ。みんなそういう野蛮な言い方をしないだけなのよ。どうしてかって、恋愛なる行いは美しくて尊いものだからよ。でも、そこには人を選別するというニュアンスも含まれているのよ。
結局、私たちは選んでいるのよ。誰でもいいってわけじゃないのよ。そして、そうさせているコアって本能に基づく欲望なんだと思う。ねえ、断言させて。欲望の目的は満たすためにあるのよ。それ以外に目的はないはず。だから、お互い見返りを求め合わなくちゃならないのよ。また、そうあるべきなのよ。ねえ、カオル、私何か間違ったこと言っている? ねえ、教えてよ! ねえ……」
「里実は間違ってないよ」と森野カオルはそっと言った。それから、スケッチブックのまだ何も描かれていない余白を見て「けど……」
「けど?」
「……」それ以上、言葉が出てこなかった。
里実ワカバは膝を抱えて丸くなり、森野カオルを見つめていた。そして、長い沈黙の末、ざらついた舌触りを紅茶で流し込んだ。
口にした紅茶はほろ苦かった。しかし、ただほろ苦いだけじゃなかった。とても複雑なテーストだった。複雑すぎて形容しようがなかった。つまり、心の中で感じたことを、全て言葉で言い表すことはできないのだ。そもそも、そんなことは不可能なのだ。所詮、言葉は不完全な人が作り出した不完全な代物だもの。完璧じゃない。むしろ完璧じゃないから寄り添えるのだ。体を預けられるのだ。さてと、その言葉とやらを使いきれいさっぱりふられることにしよう。
そして里実ワカバは、募る思いを告白しはじめた。ゆっくりと、丁寧に、文字通り言葉をかみしめながら。
予期した答えが、森野カオルの口から返ってきた。その瞬間、夜が深まっているなんて思えなかった。時間という意味が失われた感覚とでもいうのだろうか? 始まりもなく終わりもない。前もなく後ろもない。今日という日は、もう無かったことにはできない。今までの関係には戻れない。そう思ったら、口をついていた。「なんてざまよ」
「ん?」
「ううん。何でもないよ」と里実ワカバは言い、はぐらかした。それから、はずんだ声で「さてと、この夏が終わったらパーカーのフードでもひっくり返すとするか」
そうすることがボーイフレンド募集中の目印であるということを、森野カオルは知らない。そうだと知っていて里実ワカバは言ったのだ。心の形を変えるには、時間が必要だもの。この夏が終わるまで片思いさせてくれ。そのくらい、わがまま言わせてくれ。
「あっ、もうこんな時間だよ、カオル。そろそろ帰った方がいいんじゃない?」
「まだスケッチの途中だよ」と森野カオルは言い、テーブルの上の腕時計を見て「終電まで時間あるし」
「カオルはドジだから、早めに行動するくらいで丁度いいの。何故って、うっかりスニーカーの紐をふんづけて、街路樹に頭をぶつけて、メガネを落として、間違えて猫を拾って、その猫に顔をひっかかれて、池に落ちて、雷に打たれて、今夜の記憶失くして、それから、それから……」
「そこまでまぬけじゃないよ」
「はいはい。わかった。わかたった」と締めくくって「ほら玄関まで送るからさ」
「チョッと里実」
「ほら急ぐ」
「待ってよ」
「待ってよじゃない。ほらほら」森野カオルの背中を押して「スニーカーの紐、ちゃんと結んでよね」
「いつもそうしているよ」
「結べた?」
「あ、うん」
「じゃあね。おやすみ。また明日」と里実ワカバは笑顔で言い、ドアを閉めた。
もちろん、一連の流れは演技である。高校時代、演劇部だったことが役に立ってしまうなんて、と里実ワカバは嘆いた。ともかく、何とか間に合った。後、数秒遅れていたら……。
そして里実ワカバは、崩れ落ちるようにしてしゃがみ込んだ。それと同時に、大粒の涙が頬をつたった。ぐしゃぐしゃな気持ちだ。けど、カオルはドアの向こう側にまだいる。声を押し殺して泣くしかない。
「里実」
外から森野カオルの声が聞こえた。優しい声だった。それが辛い。「ねえ、一人で泣かせてよ。これ以上、優しくしないでよ。おねがいだから」
森野カオルはドアにもたれると宙を見据えた。しばらくそうしていた。それから、スケッチの続きをはじめた。
……
やがてスケッチは完成した。レトロガーリーなシャツワンピースに身を包んだ里実ワカバのスケッチである。
それを郵便受けに入れると、森野カオルは静かに言った。
「おやすみ。また、明日」
しかし、返事は無かった。ただ、すすり泣く声が聞こえるだけだった。
誰かを好きになるということは、時として誰かを傷つけることになる。それでも人は、誰かを好きでいたい。最低だ、と森野カオル。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕