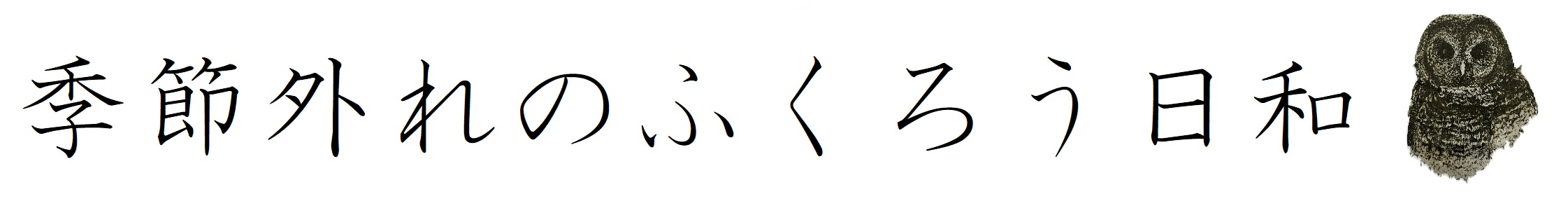作:武田まな
〔一年前〕
図書室に本を返却し終えた森野カオルは、おっとり刀でエマ先輩が待つ屋上へと向かった。しかし、その足は屋上へと続くカフェオレ色の扉の前で止まった。それは扉の隙間から聞こえてきた声が原因である。一人はエマ先輩。もう一人は知らない男。
「なあ、杜葉。あんな年下のまぬけな奴とつるんで何が楽しいんだよ」
「私たちのことは、あんたには関係ないでしょ」とエマ先輩は、投げつけるように言い返した。
「関係があるから、わざわざ忠告しに来たんだよ」
「どこがどう関係あるってのよ。あんたと、私」
「だから、それは、その……」
「ほら、関係ないじゃない」とエマ先輩は、切って捨てた。「私、デリカシーのない男って大嫌い」
「じゃあ、何であんなことしたんだよ」
「あんなことって何よ」そして、ムッとした声で「あんたとなんか、何でもあってたまるか」
「クソ、忘れたなら話してやろうか? 一か月前のコンパニーのこと」
男の話を遮るようにしてエマ先輩は言った。
「ねえ、ハッキリ言わせてもらうけど、あんたと私が付き合ってもいないのに、付き合っているとか出鱈目なこと流布するの、やめてちょうだい。それ、あんたの仕業だって知っているんだから、私。それにコンパニーで、ついアルコールを飲み過ぎてしまった女の子に対してあんたがしたことは、私の中の最高裁判所で有罪が確定しているの。おわかり? 有罪よ。ユウザイ。どう転んだってもう無罪にはなりやしないのよ。ほんと、あんたって最っ低。もう二度と、私に関わらないで」
……
まるで楔でも打ち終えたかのような沈黙が、屋上に鳴り響いていた。そんな中、エマ先輩はナイフのような鋭い視線を男に浴びせ続けた。
沈黙と視線に耐えかねた男は、フェンスを蹴飛ばして悪態を吐くと、その場を後にした。そして、ペントハウスの扉を乱暴に開け閉めすると、踊り場にいる森野カオルと出くわした。
「どけ、邪魔だ」と男は言い放ち、森野カオルを突き飛ばした。そして、階段を下りようとしたが、森野カオルに呼び止められた。
「おい」
「何だと」男は立ち止まって振り向いた。「年下のくせに生意気な口のきき方しやがって」
そう言われ、森野カオルは男の胸ぐらを掴んだ。しかし、それがまずかった。両手がふさがったからだ。それに気が付いた時は、もう遅かった。男の右フックが顔面を強打していたからだ(案の定、メガネは吹っ飛ぶ始末だった)。
どちらかというと、痛みというよりか衝撃音に驚いた。が、それでも冷静だった。だから次に備えることができた。しかし、次はなかった。そのおかげで足元の赤いドット模様に気が付いた。
赤いドット模様の数は、見る見るうちに増えていった。そして、硬く冷たいコンクリートに熱が奪われていくと、黒く変色して固まろうとしていた。
二人はそんな赤いドット模様を見つめていた。
ややあって、男は小さな声で「先に手を出した、お前がいけないんだ」と言い残し、そそくさとその場を後にした。
森野カオルは何も言い返さなかった。また、追いかけようともしなかった。そんなことよりエマ先輩が心配だったのだ。ともあれ、ティッシュを鼻に詰め込むとメガネを拾った。その時、片方のレンズが外れて落ちた。
止血している間、二人の会話が森野カオルの胸をかすめた(コンパニーで何があったのだろう?)。しかし、物事の重心はもうそこにないように思えた。物事の重心があるのは、扉の向こう側、すなわち今のエマ先輩である。過去のエマ先輩じゃない。
そして森野カオルは、カフェオレ色の扉をそっと開けた。すると、光の洪水に目が眩んだ。
目が慣れてくると、辺りの景色が見て取れた。青空、入道雲、熱を帯びたコンクリート、濃い影。まさに季節はあの夏である。それなのにエマ先輩の後姿は、寒さに凍えているようだった。
つづく
信州のアウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕