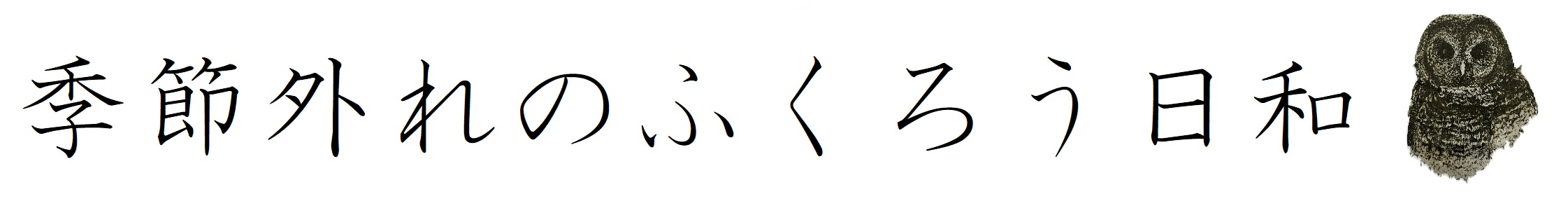作:武田まな
「あのね、さっきのアナグラムのことだけど。実は正解なの」
「まあ、自信ありましたからね」と森野カオル言い、コーヒーを口に運んだ。少し酸味があってフルーティーなフレーバーだった。「エマ先輩。僕にできることありますか?」
「ありがとう。じゃあ、遠慮なく」
エマ先輩は二つのスケッチをテーブルの上に並べて、今夜、遭遇した出来事を話しはじめた。
話していく内に不安は溶けていった。そして、全て話し終えてからコーヒーに映った自分を見て言った。「一度も訪れたことがない場所なのに、その場所のことを知っているって経験ある?」
「今まで色々な場所にロケーションハンティングに行ってきましたけど、そういった経験、ないですね」
「そう……」もしかしたら、と思っただけのこと。「そうだよね」
「エマ先輩。そのスケッチの場所、見覚えあるんですか?」
「見覚えはないんだけど……」
「けど?」
「その場所が、どこかに存在しているような気がするのよ」とエマ先輩は言い、心に留めておいてといった風に言葉を重ねた。「何となくだけど、そんな気がするの」
「それ、直感とかですか?」
よくわからないという意味を込めて、エマ先輩は首をすくめた。
「じゃあ、アプリオリなるもの?」
「どちらかといえば、そっちの方が私の感じているフィーリングに近いかも」
「アプリオリか……」と嘆いてから、便箋とシステム手帳を手に取りスケッチを眺めた。線に迷いがない。その場で描いた特有の説得力も感じる。大いに不思議。
「ねえ、何かわかりそう?」
「ふと思い出したんですけど」
「どんなこと?」
「記憶って遺伝するみたいですよ」
「記憶が遺伝?」
「ええ、ただし意識のレヴェルじゃなくて、本能のレヴェルに遺伝するみたいですが。だから、自分にどんな記憶が遺伝しているのか、知る由もないみたいですけど」
「今の話、本能を無意識と置き換えても構わないのかしら? つまり鳥が空を飛び、魚が水の中を泳ぐのは、本能を意識して知るんじゃなく、本能を無意識に知りそうしているから、とかうんぬん」とエマ先輩は、用心深く尋ねた。
「そうですね。目に見えるものを意識、だとするならば、本能や無意識は目に見えないものと置き換えられますからね」
「ねえ、カオル。ちなみにそれどこから仕入れた知識なの?」
「忘れました」と森野カオルは、あっさり答えた。
この際しょうがないか、とエマ先輩。「ともかく、今言ったことをファジーにまとめると、私に遺伝している記憶が、ひょんなことからフラッシュバックして無意識にスケッチさせた、というようなこと?」
「そうですね。枯れ木も山の賑わい的な仮説ですが」
「枯れ木も山の賑わい的な仮説か」とおうむ返ししてから、溜息交じりに「でも、何も無いよりかはましね」
「あのエマ先輩?」
「ん?」
「このスケッチの場所、探してみませんか?」と森野カオルは言い、二つのスケッチをエマ先輩に向けた。
「へっ」と口をあんぐり開けて「でも、探すってどうやって?」
「先輩、学生時代に言っていたじゃないですか? 可能性を手放さないために図書館があるんだって」
「それレポートの提出期限を守るコツとして、アドバイスしたセリフよ」
「この際、拡大解釈しませんか」
「あきれる」とエマ先輩は言葉通り言い、クスッと笑った。「それで図書館とスケッチ、どう関係してくるわけ?」
「図書館の地形図を見て探すんですよ。その為に、まずこのスケッチを地形図に作り直します。そっち方面に詳しい友人の力を借りて作ってみます。それから、出来上がった地形図をもとに、二人で探すってわけです」
「途方もない作業に思えるんだけど?」
「謎めいたまま立ち止まっているより、どこかに向かって進んでいる方がいいじゃないですか。まあ、これも枯れ木も山の賑わい的な提案ですけど」
エマ先輩は人差し指で唇を叩きながら、森野カオルの表情を伺った(やっぱし、レモンの気配を感じる。胸がスッとするのもそのせいか)。
それから、エマ先輩は膝を抱えて丸くなり、祈るような目を森野カオルに向けた。まるで小さな子供が、夏の午後の予定を尋ねるみたいに。
「もし、見つけたらどうするの?」
「その場所に行ってみましょう」
「その場所に行ってどうするの?」
「とりあえず、僕はスケッチでもします。僕にとってスケッチする行為は、鳥が空を飛び、魚が水の中を泳ぐのと同じですから」
「その比喩、どこかで聞いたことがあるわ」
「奇遇ですね。僕もどこかで聞いたことがあります」
「あら、そ」と簡素に相槌を打って「じゃあ、私は桟橋の先端から紙飛行機でも飛ばそうかな。その後は、レモンにでも齧りつくわ」
「じゃあ、決まりですね」と森野カオルは、締めくくった。するとホッとしたせいで大きなあくびが出た。眠い。
次の瞬間、眠気とやらは遥か彼方に吹っ飛ぶことになった。
「ねえ、泊まっていく?」
「えっ」
そう提案したエマ先輩自身、驚愕していた。というのも、そもそもそんなことを言うつもりは無かったのだ。少し仮眠していく? と言うつもりだったのだ。カオルのあくびを目の当りにして、つい口が滑ったのだ。
「うげ! そういう意味じゃなくて。えっと、だから、そういう意味じゃなくて」
ともかく、この状況をはぐらかすため、エマ先輩はバナナの話をはじめた(カオルが来る前に目を通していた本から引用したのだ)。それにしてもよりによってバナナ? 蠱惑的じゃない。私のあほんだら。
「あ、そうだ。カオル、知っていた? 近い将来、私たちが普段食べているバナナは、絶滅して無くなるかもしれないのよ。一応、これは科学的な予言でもあるのよ。バナナって桜のソメイヨシノと同じで、突然変異した品種のクローンだから、病気に対して抗体を持ち合わせてないわけ。実際、病気になって絶滅したバナナの品種だってあるのよ。だから、残された数少ないバナナの品種たちが病気になって絶滅すれば、もう食べられないのよ」
その話を受けて森野カオルは、スーパーマーケットの夜のことを思い出していた。あの日、エマ先輩の艶を帯びた唇から発せられた声は、一年ぶりに聞く声だった。にもかかわらず、そう感じなかった。二人の間に一年という時間が存在しているなんて、そう思えなかったのだ。つまりこの一年で何かを失うことはなかったのだ。そう考えていると、エマ先輩のブラウスが目に留まった。これ以上、長居をすれば明日の仕事に差支えてしまう。学生だってやれば社会人の気持ちになれるのだ。
「ねえ、驚いたでしょ? 今のバナナの話」
「たまげました」
「で、何を見ていたの?」
「コットンです」
「またコットン」
「あのエマ先輩、そろそろおいとまします」
「あ、ん、そうだよね」とエマ先輩は、返事をして本棚の片隅に鎮座する腕時計に目をやった。もうこんな時間だもの。帰るのは当然。お互い明日に差支えてしまう。でも、明日に私はまだいない。私は今ここにいる。今この瞬間ここに。それだけは確かだ。五感で感じるもの。不確かなのは、明日の方なのだ。五感で感じられない。だから都合のいい言い訳として、誰もが気軽に使うのだ。また今度、また明日と……。
「先輩? どうしました?」
「ううん、何でもないわよ」
「じゃあ、明日の夜、電話しますね」
「うん」
「コーヒー御馳走様でした」
「お粗末様です」何言っているのだろう、私。それにカオルだって。
森野カオルは立ち上がると玄関に向かった。そして、スニーカーに足を滑り込ませると、解けていた紐を結びはじめた。
エマ先輩はその様子を静かに見守った。
スニーカーの紐を結び終えた森野カオルは、首をすくめてエマ先輩に告げた。
「おやすみなさい」
エマ先輩は小さく手を振り「ええ、おやすみ」と返事をした。また「ありがとう」とも。
森野カオルはドアを開けて外に出た。それから、ドアをそっと閉めた。
ドアが閉まる寸前、「気を付けてね」とエマ先輩。
雨はすっかりやんでいた。静かだ、と森野カオル。それから、駐車場に向かおうとしたのだが、どういうわけか足が動かなかった。
「先輩。鍵、かけて下さい」
「……」
「じゃないと」一歩が踏み出せない。
「……」
次の瞬間、鍵の音ではなく小さな声が森野カオルの耳に届いた。
「一年ぶりに再会したあの夜。スーパーマーケットにレモンを買いに行ったの、私。けど、カオルの声を聞いていたら、レモンを買うの忘れちゃったの。ううん、その必要がなくなったの」
続けてエマ先輩はこうも言った。
「あいにく今レモンを切らしているの。だから、いなくなると困るの……」
つづく
信州のアウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕