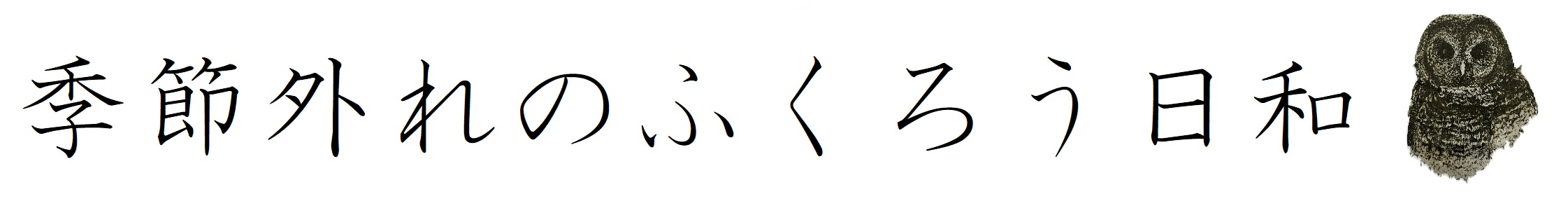作:武田まな
エマ先輩からの提案で、ランチは図書館の飲食スペースで食べることになった。というのも、トートバッグの中から現れたのが、クロワッサンサンドと、アイスコーヒーと、レモンだったからである。森野カオルは伏線が回収できてカラフルな気分になった。なので、口をクロワッサンサンドでいっぱいにして感想を述べ立てた。
その間、エマ先輩はとぼけた顔をしてレモンに齧りついては、舌なめずりしていた。レモンはいつもより酸っぱかった。香りもいつもよりキリッとしていた。それだけじゃない。青くもない風が青く見えたりする。何よりバカみたいに暑いときている。どういうわけか、五感が研ぎ澄まされてしまったのだ。それが妙に恥ずかしい。だから、呑気に感想を述べ立てている輩の口の中に、レモンを一房放り込んで黙らせることにした(おいそれと褒め過ぎだ)。
次の瞬間、森野カオルはけたたましくむせはじめた。
この日を境に週末のロケーションハンティングは一時小休止となり、図書館通いがはじまった。自動ドアをこじ開ける。いつもの席に腰を落ち着かせる。世界地図に目を落とす。ランチを食べる。再び世界地図に目を落とす。そして夕方、図書館を後にする。スーパーマーケットで食材を買う。エマ先輩のアパートに向かう。二人で夕食をこさえて食べる。眠る。起きて明けの明星を眺める。
そんな風にして二人は、ただただ予見可能な日常を風流に繰り返していた。しかし、ふとした刹那、エマ先輩の目前にクエスチョンマークが舞い降りるのであった。
それというのは、森野カオルの腕時計のことである。相も変わらず身に着けていないのだ(まったくカオルときたら……)。しかし、風流な日常が舞い降りたクエスチョンマークを消し去るのでもあった(はてさてカオルときたら……)。
やがて夏が中盤戦を迎える頃、驚くなかれ、地形図と類するポイントが幾つか見つかった(しかし、どれもこれも決定打に欠けた)。そうなれば、予見可能な日常と別れを告げ、そのポイントやらに足を運んでみるうんぬん話が展開するはずである。
しかし、二人は相変わらず図書館通いを決め込んでいたのだ。鳥が空を飛び魚が水の中を泳ぐといった風に。つまり、そうする理由は言語体系の外側にあるのだ。
「金星のことを思うから、金星や太陽系は存在するのよ」とエマ先輩は、しみじみ言った。
今朝は曇りで明けの明星は見えない。
続けてエマ先輩は、こうも言った。
「見えるか、見えないか、違いはそれだけ。たったそれだけなの。でも、金星や太陽系のことを思わなければ、それは存在しなくなってしまうのよ。すなわち、それがあるから、それはある。それがないから、それはない」
森野カオルはそっと相槌を打った。そして、ベッドから垂れているエマ先輩の右腕をスケッチしながら思った。淡い朝の光を浴びた金色の産毛たちは、どんなに魅力的なアクセサリーなんかよりも美しいと。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕