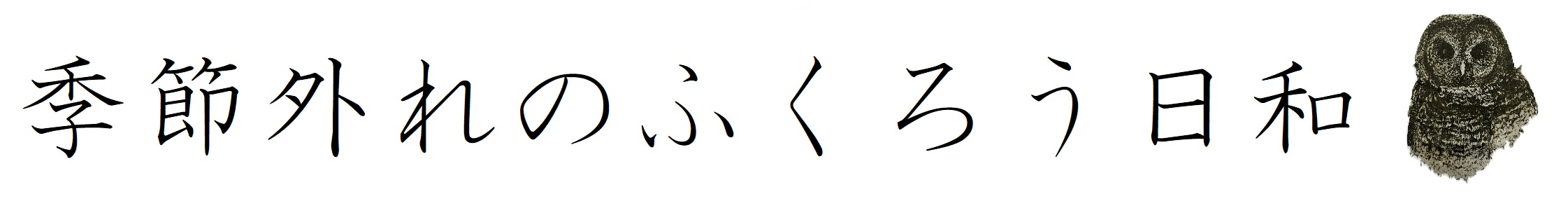作:武田まな
〔現在〕
「おーい。森野、里実くん」
そう呼ばれた二人は、苦笑いを浮かべた(声がデカすぎる。いらぬ注目を浴びてしまったではないか)。
高橋は無人島からたまたま通りかかった船に向かって、救助を求めるといった風に両手を大きく振っていた。
片や、その隣ではノースリーブのワンピースに薄手のカーディガンを羽織ったエミカが、ビールジョッキを片手に投げキッスをしてよこした。通りかかった船は、前者より後者の存在に気付くと相場は決まっている。
アウトドア関係の会社がプロデュースしたビアガーデンうんぬんビルの入口に掲げてあるシックな看板の隅に、小さな文字で簡素に書かれてあった。したがって、テーブル、イス、ランタン、食器類、スタッフのユニフォームに至るまで、その会社の商品で統一されていた。時折、アウトドア系の雑誌の中でこういったシチュエーションを目にするが、実際に目の当りにすると少し落ち着かない気持ちになるな、と森野カオルは思った。
「ねえ、あれ」と里実ワカバは、森野カオルのシャツの裾をつまんで言った。
彼女の視線の先には、大きくて真っ白なカンバス生地が張られてあり、山だの川だの映像が映し出されていた。
「たまげた。あの手のビアガーデンとは、ずいぶん違うね」と森野カオルは、唸るように言った。
「そうね。客層もBGMもイカしているわ」
そして二人は、高橋とエミカがいる席に腰掛けた。
高橋は鼻の下を擦ると自慢げに言った。
「ここ悪くないだろ?」
「うん。すごく良い。ねえ、意外。高橋君がこんなハイセンスなお店を知っているだなんて」と里実ワカバは、はしゃいで言った。「意外すぎて、何だか胸騒ぎがするわ」
「このお店、バイト先の先輩に教えてもらったんだって」とエミカは、のんびり言った。「だから驚く必要ないわよ。ワカバ」
「おっと、それを聞いてホッとしたわ。サンキュー、エミカ」
二人はけらけらと笑い合った。
程なくして注文をとりにきた店員に、里実ワカバはビールを、森野カオルはペリエを注文した。
やがて飲み物が運ばれてくると、夏のはじまりに乾杯してから改めてお喋りがはじまった。
お喋りはいつもより洗練されたものだった。ようするにシチュエーションに流されたのだ。一介の大学生ならば、当然のこと。
そして、そんなお喋りがひと段落した折、高橋が言った。
「なあ、森野。野球観戦のチケット無駄にしたんだって?」
その時、女子たちはティラミスについて熱心に語っていた。したがって、今、高橋が何を尋ねたのかは知らない。
「チケットのことは、昨日の夜、里実から電話で聞いたんだ。だから、無駄にしたくて無駄にしたわけじゃないさ」と森野カオルは、あっさり答えた。
「じゃあ、昨日は朝っぱらから出かけていたってのか?」
「朝から晩まで出かけていた」一度、帰って来て、その後、また出かけたんだっけ。だから眠いや。
「そっか」と高橋は言い、ビールを口にした。それから、カンバス生地に映し出された雄大な北アルプスの山々めがけて、チューインガムをパチンといわせた。
「なあ、高橋」
「ん?」
「その癖、卒業するまでには直しておいた方がいいぞ。友人からの忠告だ」
その癖というのは、チューインガムを嗜みながらビールを口にするという謎めいた行為である(二年前のキャンプで興じた罰ゲームがその発端である。罰ゲームがあらぬ嗜好を開花させたのだ)。
「ふん、凡人め」と高橋は、投げつけるように言い返した。それから、何かを思い出したような表情を浮かべて「そういえば、森野。二年前のキャンプの頃って、まだアルコール飲んでいたよな?」
「まあな」と森野カオルは答えて、ペリエを口に運んだ。
「飲まなくなった理由、何だっけ?」
「前に話したと思うけど忘れたのか?」
「人間ってそんなもんだ。ガハハ」
森野カオルは簡素に理由を述べることにした。
「単にそう決めただけだよ」
「へえ、単にそう決めただけか」と高橋はおうむ返しして、チューインガムをパチンといわせた。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートを綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕