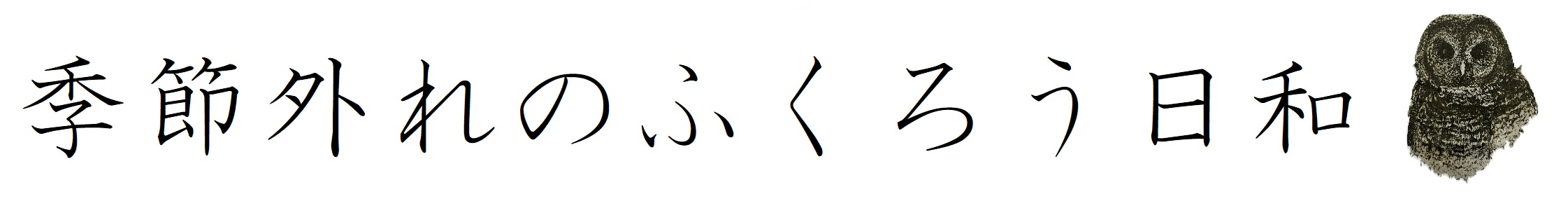作:武田 まな
金曜の夜、パーティーズオーバーにはまだ早い時間、スーパーマーケットの雑誌コーナーにシックないでたちの女性が一人、あの手の週刊誌に目を落としていた。残念ながらここはモダンなレストランだの、ロマンチックなBARだのではない。いわゆる庶民的なスーパーマーケットの代表みたいなところである。ワンレンボブの隙間からちらつく艶を帯びた唇は、銀ブラしてこそ映えるのだ、うむ。
森野カオルはバナナを一房手に取ると、パンが潰れないよう買い物カゴの中へと滑り込ませた。と同時に、名前を呼ばれたような気がした。てか、はっきり呼ばれたのだ。だから手元が狂ってしまいパンが少し潰れた。
「ねえ、森野カオルじゃない? 久しぶり」
そう彼を呼び止めたのは、シックないでたちの女性だった。
「エ、エマ先輩だったんですね」と森野カオルは、ドギマギ返事をした。そして、ためつすがめつ眺めていたにも関わらず、知人だということに気付かなかった手前、表情を工夫する必要があった。
エマ先輩は週刊誌をマガジンラックにもどすと、森野カオルの所に歩み寄った。それから、けんもほろろに言った。
「なに? その表情」
「わかりませんか? オシャレな先輩と再会できて、嬉々としているんです」
「あきれた」とエマ先輩は言葉通り言い、肩をすくめてから森野カオルの足元に視線を落とした。スニーカーの紐がだらしなく解けている。「ねえ、その靴紐、誰のか見覚えあるかしら?」
「ええ、もちろん」と森野カオルは、こともなげに答えた。それから、スニーカーの紐を結ぶにあたり、買い物カゴ、エマ先輩、それぞれに目をやった。
「しょうがないわね。持っていてあげるわよ」
「かたじけないです」と森野カオルは礼を言い、エマ先輩に買い物カゴを手渡した。
「相変わらず図々しい奴だこと」ホッとするじゃない。それは言葉にしなかった。
「この履き崩したファッション、流行ればいいのに、ガハハ」
エマ先輩は鼻を鳴らしてコメントを省略した。
スニーカーの紐を結び終えた森野カオルは、エマ先輩から買い物カゴを受け取ると言った。
「それにしても久しぶりですね。先輩」
「私が大学を卒業して、かれこれ一年経つから一年ぶりってことか」
「もう一年経つのか。アッという間だったな」と森野カオルは、目を細めて言った。
「その言い草、おっさん臭いわよ」
「ありがとうございます」
「別に褒めてなんかないわよ」
「それ、わかっていますから」
「まったく森野ときたら」
それから、エマ先輩は髪を一房もてあそびながらレモンに視線を投げた。照明を浴びたレモンは、どことなく手榴弾に見えた。もしかしたら手榴弾をデザインした輩は、レモンを参考にしたのかもしれないと思った。ん、そういえば私、何か買うものがあってスーパーマーケットに来たんだっけ。けど、その何かが思い出せないときている。さてはて……。
「あの、エマ先輩」
「ん?」
「一つ尋ねてもいいですか?」
「お好きに」
森野カオルは咳払いをしてから言った。
「何かの集まりでもあったんですか?」
「何かの集まりって?」
「だって、ほら、シックな格好しているものだから」
エマ先輩は反射的に自分の服装を確かめた。それから「森野には関係ないでしょ」とだけ言い目を伏せた。
「大人の事情ってわけですか?」あろうことか、おこがましいことを尋ねてしまったようだ。
「バカ。うがった見方をするんじゃないの」
「へーい」と無邪気に返事をした。
「この話はこれでおしまい。わかった?」とキッパリ言い、艶を帯びた唇を硬く閉ざした。だが、それは一時。「それはそうと、森野。買物の途中なんでしょ? 折角だから付き合ってあげようか?」
「じゃあ、お言葉に甘えさせていただきます」
「うむ」とエマ先輩は締めくくり、パンプスをコツコツと鳴らしながら生鮮食品売り場に向かって歩きはじめた。まるでランウェイを歩き終えたモデルが、控室に帰るみたいに。
二人は食材を物色している間、会話らしい会話を交わさなかった。ただ「はい」とエマ先輩から手渡された食べ物を、森野カオルは受け取りパンがつぶれないよう買い物カゴの中へと滑り込ませるだけだった。そうやって予見可能なシークェンスを繰り返していたのだ。
やがて二人はレジスターに並んだ。
会計を待っている間、森野カオルは自分の格好を確かめてみた。一介の大学生のスタンダード、パーカーにジーンズという格好である。でもって不釣り合いな格好の男女が、夜のスーパーマーケットで肩を並べている図式でもある。とくれば落ち着かない気持ちになるはずなのだが、さてはて……。
「ねえ、森野」とエマ先輩は、ポツリと言った。
「なんですか?」
「あのさ。パンは最後にカゴに入れるものよ」
ことごとく潰れてしまったパンを見つめて、森野カオルは唸るように言った。
「なるほど」
「まったく森野ときたら」エマ先輩は首をすくめた。するとフライド・ハンバーグなるポップ広告が目にとまった。「あれってメンチカツのことよね」
「まあ、そうですね」
エマ先輩は熱い煎茶をすすった後に出すような吐息をもらした。
「スタイリッシュな表現ね」
「あの先輩。ありがとうございます」
「ん?」
「買い物に付き合ってくれて。それとパンの扱いは以後気を付けます」
そう告げられただけなのに、胸にクるものがあった。が、エマ先輩はその理由を探そうとはしなかった。
「会計、森野の番よ」
「あ、はい」
二人は食べ物に数字が与えられていく様子を静かに見守った。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートと情報を綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕