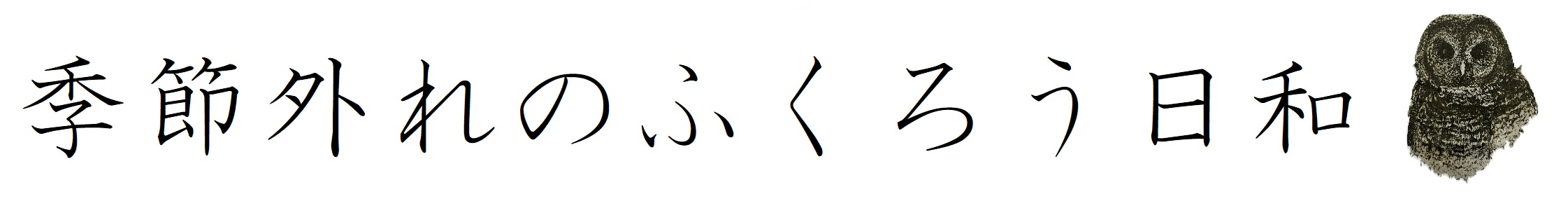作:武田まな
エマ先輩はあっさり首をすくめると、芝生をねじったり、つねったり、あれこれ楽しんだ。断言しよう。今、感じているこの気配。学生時代、屋上で感じていたあの気配だ。しかし、明日になれば仕事だの、満員電車だの、人間関係だのに沈んでしまい、この気配から遠のいてしまう。離れたくない。このままでいたい、ああ……。
そしてエマ先輩は、人差し指で唇を軽く叩きはじめた。一回、二回、三回、と叩いている時たった。森野カオルの顔が視界に飛び込んだ。
「先輩。紙飛行機、飛ばしてください。スケッチするんで」
「へっ」藪から棒に、どういうこった。
「二度は言いませんよ。ほら」
「わ、わかったわ」そう返事をすると、エマ先輩はバッグの中から便箋を取り出して紙飛行機をこさえた。それから、ムクッと立ち上がり人差し指をおっ立てて風を読んだ。今から紙飛行機を飛せると思うと胸がじんわりした。なんたって外で飛ばすのは一年ぶりだもの。ん、この風、悪かない。今だ!
どうして一年もの間、私は飛ばそうとはしなかったのだろう。ただただこの一年、予見可能な未来が訪れる日常、という内側に沈んでいるだけだった。いつから心の形を変えてしまったのだろう? ともあれ、ま、いっか。今日はそんな日常とは違うもの。飛べたではないか。
そして、森野カオルのスケッチブックに、紙飛行機と、エマ先輩が描かれた。スケッチブックの中の彼女は、パンプスを脱ぎ棄て裸足になり、両手を真横に大きく広げていた。まるで白い夢に出てくるヒロインみたいだな、と森野カオルは思った。
その思考を感じ取ったかのように、エマ先輩は振り向き、私だけを見て! と言わんばかりに声をあげた。「あのさ、森野」
「なんですか?」
「私たちって、私たちを取り巻く物事との関係性から、この私の存在を認識しているわけじゃない?」
「まあ、そうですね」
「森野が話す言葉だとか、草木の匂いだとか、目に映る景色があるから、今、私はここにいるんだって、はじめて実感できるわけじゃない? もしも、何も聞こえなくて、何も感じなくて、何も見えなければ、この私の存在を実感することは、できないでしょ? ねえ、何が言いたいのかって。誰でもいいってわけじゃないの。誰とどんな関係性で、この私を認識するのか。それって、わがままに聞こえる?」
「いや、そんな風に聞こえませんよ」と森野カオルは言い、目をパチクリさせて「それより、突然どうしたんですか?」
「別にどうもしないわよ。ただ……」
「ただ?」
一呼吸置くと、エマ先輩は心がある声で言った。
「私の纏っていたい時間が、今ここにあるのよ」どうしてそんなことを、森野に告げたのだろう。そう思うと、無性にレモンへ齧りつきたくなった。さりとて、ここにレモンは無い。ことことに至って今は、彼の反応を待つしかない。
ややあって、森野カオルは口を開いた。
「僕の纏っていたい時間も、今ここにあります」
「じゃあ、二人は同じ空模様ってわけね」
「て、ことになりますね」
言ってくれるじゃないか、森野カオル。となれば、この時間を纏い続けていたい。そのためにはどうすればいいのだろう? とエマ先輩は考えた。考えあぐねた末、あることを閃いた。私の腕時計の時間を、彼の十二分遅れている腕時計の時間に合わせてみよう。そうすれば、この時間を纏え続ける。きっとそうだ。
それから、エマ先輩は森野カオルの目前に来て屈むと時計のことを提案した。
「いいですよ」と森野カオルは、二つ返事で引き受けた。「けど、遅らせるのは一分とかにしませんか? エマ先輩、社会人だから、何かと困るだろうし」
「それじゃあ意味ないの」キッパリ言って「どうしてって、尋ねちゃ駄目よ。大事なエッセンスが吹き飛んじゃうから。ねえ、私の言うとおりにして。おねがい」
エマ先輩の野性的な瞳は、小さなプラネタリウムを思わせた。「わかりました。じゃあ、生活するうえで、色々と気を付けてくださいね、エマ先輩」
「ありがとう。十二分に気を付けるわね」十二分だけに、とは言うまい。それこそエッセンスが吹き飛んでしまう。
そしてエマ先輩は、自分の腕時計の時間を十二分遅らせた。すると、角砂糖の中の空気みたいに甘くて、夏の朝の雫みたいに透明で、水面に広がる波紋みたいになめらかな気分になった。思った通りだ。
続けてエマ先輩は、首を傾げると言った。
「ねえ森野。来週はどこにロケーションハンティングに行こっか?」
「来週って、まさかあの来週?」
「来週ったら、あの来週しかないわよ」
軽く顎が外れそうになった。まったく、エマ先輩ときたら。「じゃあ、湖はどうです?」
「それ、グレイトアイデアじゃない」とエマ先輩は言い、目を細めて「とっても楽しみ」
「そうだ。今度はレモン持って行きましょうよ。それにコーヒーと、クロワッサンも」
「正気じゃないわ」舌なめずりして「ゾクゾクしちゃう」
「よだれ出ていますよ。先輩」
「げっ」
翌日、世の中の並列化された時間とは別の時間を纏った二人に、おかしな現象が起こった。それは、ありとあらゆる自動ドアが開かなくなる、というものだった。
しかし、二人はそのことに対して無頓着だった(翌日以降もそれは続いたのだが)。もっとも手動で自動ドアをこじ開けるか、前を歩いている人に続けばよかっただけのこと。したがって、大きな問題だと認識せず切って捨てたのだ。
とはいえ、それがはじまりだったのだ。謎めいた出来事との接触。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートと情報を綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕