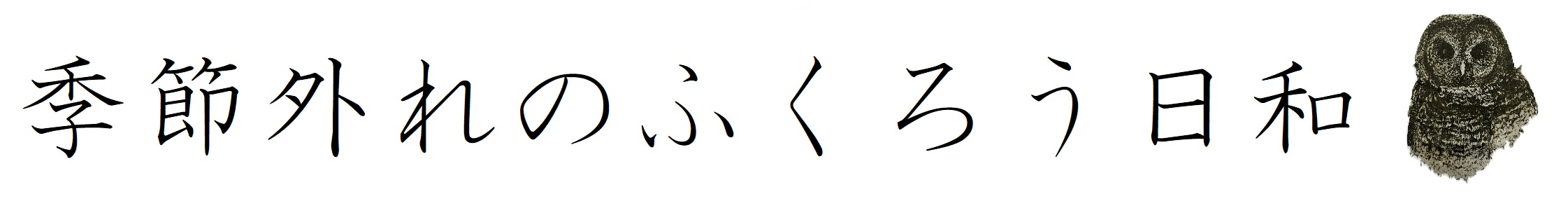作:武田 まな
〔一年前〕
その日、予定していた講義を終えると、エマ先輩は『白いモラトリアムサマー』なる本を拝借するため、大学の図書室に足を運んだ。
目的の本を探していると、エマ先輩の足はスッと止まった。それは『白いモラトリアムサマー』なる本を見つけたからではなく、本棚の隙間越しに見える不届き者がその原因であった。
不届き者は窓際の席に腰を落ち着かせていた。そして、地図を机上に広げ外の景色を眺めていた。別段、それだけでは興味をひくとこはなかった。図書室ではよく見かける光景である。ところが、驚くなかれ彼は、周囲の様子を気にすることもなく鼻歌なんぞ歌っていたのだ(まさに不届き者ではないか)。そのヴォリュームは小さかったが、図書室というおごそかな空間では充分であった。したがって曲名も『仰げば尊し』だと判明する。しかし、今は六月である。卒業シーズンではない。つまるところ『季節外れの仰げば尊し』とでも言うべきか。
エマ先輩はハッと我に返ると、辺りを見回した。すると、他に観客は三人いた。銘々、複雑な表情を浮かべて彼に視線を注いでいた。さも明日の朝、空から毛玉が降ると天気予報士に告げられた人のようである。なんとまあ……。ともあれ、このまま不届きもの様子を観察することにした。
観察の結果、わかったことと言えば、意識して鼻歌を歌っているのか? 無意識で歌っているのか? まったくもって不明である、ということだった。てか、どうして『仰げば尊し』なんだ。机上に広げてある地図とは、無関係ではないか。疑問は募る一方だ。嗚呼……。
結局、何も分からないまま曲は終わりを告げた。
静かだ、とエマ先輩。そして、目の前の本棚に視線を移した。すると『白いモラトリアムサマー』なるタイトルの本が目に留まった。明日、空から毛玉が降ってくるかもしれない。そしたら、どうしてくれる。
数日後、再びエマ先輩は『仰げば尊し』を耳にした。それは、あと一五分で金曜最後の講義が終わろうとしている時だった。
エマ先輩はペンシルをもてあそびながら、ぼんやり腕時計に目を落としていた。すると、例の鼻歌が聞こえてきたというわけだ。言わずもがな曲名は、あの名曲である。しかし、今回はあの時と違い渋くルバートである。
二度目となると、エマ先輩はにんまり笑う始末だった。誰もが明日の朝、空から毛玉が降ると天気予報士に告げられた顔をしている最中。
「どうしたの? エマ。もしかして、アレそんなに可笑しい?」
隣に座る友人の優子がそう尋ねた。
「まあ、ね」とエマ先輩は、けろりと答えた。
「彼、随分変わっているわね」
「かもね」
「ねえ、エマ。彼のこと知っているの?」
「彼のことは知らないけど、あの鼻歌を耳にしたのは、これで二度目よ」
「常習犯なの?」そう優子はせっつくと、目をパチクリさせた。
「おそらくね」
「ああいうタイプ。私はチョッと苦手かも」
「そう?」とエマ先輩は言い、彼の背中を見つめて「チャーミングじゃない」
「えっ」優子の息が止まった。
「冗談よ。ジョウダン」
「もう、からかわないでよ」
その直後である。彼の鼻唄はあらぬ効果を発揮することとなった。
というのも、彼の渋い鼻唄のせいでアカデミックな雰囲気が冷めてしまい、終了時間を待たず講義が終わったのである。そして、柵の中から野に放たれた羊の群れよろしく男共は、彼の背中をポンと叩き階段教室を去って行くのであった。その行為は、彼の功績を称えるものであった。が、当の本人はその状況を理解できずにいる模様。したがって階段教室に残り宙に向かって問い続ける羽目になった。
「グッドラック」
エマ先輩は彼の背中に向けて言葉を放った。
「ん、今何か言った?」
前を歩く優子が振り向くと言った。
「ううん。何も言ってないわよ」とエマ先輩は言い、眉を持ち上げてみせた。
「そっか」
「そうとも優子君」
「何それ、ハハ」
それ以来、エマ先輩は彼のことを『仰げば尊しの彼』と命名した。
つづく
アウトドアにまつわるショートショートと情報を綴っています。
よかったら覗いてみてください↓
他の作品はこちら↓
無料で読める小説投稿サイト〔エブリスタ〕